あらすじ
愛する夫の命を、その手で奪った日。絶望する紗季の前に現れたのは、亡き父の弟子であった、心を閉ざした天才棋士・岸波悟。彼は自らを世間を震撼させる怪物『ファントム』へと変える、あまりにも完璧で、残酷な計画を始動させる。
その偽りの犯行声明に、ただ一人、悲劇的な『棋譜』を読み解く男がいた。かつてのライバル、速水恭介。究極の自己犠牲か、それとも狂気か。天才たちの、魂を賭した盤上のゲームが今、始まる。
登場人物紹介
水原 紗季(みずはら さき) 物語の始まりとなる『罪』を犯す女性。著名な芸術家であった夫を、苦しみから解放するために安楽死を手伝う。岸波の計画によって守られる存在となるが、その巨大な自己犠牲と、自らの罪との間で苦悩する。
岸波 悟(きしなみ さとる) 心を閉ざした元・天才棋士。紗季の罪を消すため、自らを怪物『ファントム』に仕立て上げ、複数の未解決事件の犯人として名乗り出る。その行動は、冷徹な論理と、常人には理解できない歪んだ愛情に基づいている。
速水 恭介(はやみ きょうすけ) 岸波のかつてのライバルで、現在は大学で教鞭をとる論理学の権威。警察に協力し、岸波が仕掛けた壮大な『対局』の唯一の読解者として、その犯行声明に隠された暗号や真の狙いに迫っていく。
村上刑事(むらかみけいじ) 警視庁捜査一課のベテラン刑事。現実主義者で、物証と地道な捜査を信条とする。速水の文学的な推理に反発しながらも、事件の異常性を感じ取り、執念で真相を追い求める。
第一章 八月の雨
**1.**
八月の雨は、熱されたアスファルトの匂いを立ち上らせていた。 水原紗季は、窓の外で灰色に煙る街の景色から、ゆっくりと視線を室内に戻した。絵の具と、そして死期の匂いが混じり合うアトリエ。壁という壁には、夫である後期(こうき)が描いた、生命力に満ち溢れた巨大なキャンバスが並んでいる。原色の赤、突き抜けるような青、ほとばしる黄。それらの色彩の奔流の中で、部屋の中央に置かれた介護ベッドだけが、色を持たないモノクロームの島のように沈黙していた。
ベッドの上で横たわる夫の目は、もはや涸れた沼の底のようだった。かつて、その瞳には創作の炎が宿り、紗季を捉えて離さなかった。だが、ALSという病はその炎を奪い、彼の精神を、動かなくなった肉体という牢獄に閉じ込めた。今や彼に残されたコミュニケーション手段は、かろうじて動く眼球の微かな動きだけだった。
その目が、必死に何かを訴えている。 紗季にはわかった。それは感謝であり、愛情であり、そして、懇願だった。もう、終わりにしたい、と。
彼女の右手は、氷のように冷たい注射器を握りしめていた。左手は、夫のかさついた手を包み込んでいる。震えが指先から腕を伝い、全身に広がっていく。これは、愛か。それとも、罪か。問いは、答えのないまま思考の淵に沈んでいく。
彼女は立ち上がり、夫の耳元に唇を寄せた。 「愛してるわ、後期さん」 夫の目が、ほんのわずかに細められた。それが、彼の最後の返事だった。
紗季は震える手で、夫の腕に針を刺した。無色透明の液体が、ゆっくりと彼の身体に流れ込んでいく。窓の外で、遠雷が低く唸った。
やがて、夫の浅い呼吸が止まる。乱れていたモニターの波形が、一本の直線に変わった。紗季は、夫の手を握ったまま、その場に崩れ落ちた。色も音も失ったアトリエに、途方もない静寂が満ちていく。雨音だけが、すべてを見ていたかのように、執拗に窓を叩き続けていた。
**2.**
どれくらいの時間が経ったのか、紗季にはわからなかった。床に座り込んだまま、動けなかった。思考は停止し、巨大な虚無が心を覆っている。携帯電話が、傍らで無機質に光っていた。
警察に、電話をしなければ。 そう思うのに、指一本動かせない。自首する? なんと言えばいい? 愛する人を、この手で殺しました、と?
彼女は震える指で、スマートフォンの画面をなぞった。連絡先リストが、彼女が失ってしまった日常の象徴のように並んでいる。友人。仕事仲間。親戚。誰にも、話せるはずがなかった。
指が、ある名前の上で止まった。
『岸波 悟』
父の、一番弟子だった男。 十数年前、若くして囲碁界の頂点に駆け上りながら、理由を語らぬまま、盤面の前から姿を消した天才。父の葬儀で会って以来、一度も顔を合わせていない。彼が今、どこで何をしているのかさえ、紗季は知らなかった。
ただ、記憶の中の彼は、いつも異質なほど静かだった。喜びも、悲しみも、その無表情な顔の奥に沈めて、ただひたすらに盤上を見つめていた。常識や感情が通用しない、別の論理で生きている人間。
なぜ、彼の名を思い出したのか。わからない。だが、今の自分を理解してくれる人間がいるとすれば、それは常識の世界の住人ではないだろう、と直感的に思ったのかもしれない。
彼女は、吸い寄せられるようにその名前をタップした。コール音が、死んだように静かな部屋に響く。三度目の呼び出し音の途中で、それは唐突に途切れた。
「……どうした」
受話器の向こうから聞こえてきたのは、記憶にあるのと同じ、低く、感情の温度を感じさせない声だった。紗季は、言葉を発することができなかった。ただ、嗚咽が喉から漏れそうになるのを、必死でこらえた。
沈黙が流れる。十秒か、あるいは一分か。やがて、岸波が再び口を開いた。
「……わかった。そこにいろ。すぐに行く」
一方的に電話は切れた。紗季は、携帯を握りしめたまま、その場から動けずにいた。
**3.**
一時間後、呼び鈴が鳴った。その音は、救済のようでもあり、断頭台の音のようでもあった。 ドアを開けると、そこに岸波が立っていた。黒いシャツに黒いスラックス。十数年の時が流れているはずなのに、記憶の中の姿とほとんど変わらない。ただ、その瞳の奥にある静寂が、より一層深くなったように感じられた。
彼は「久しぶりだな」とも「ご愁傷様」とも言わなかった。紗季の横を通り抜け、部屋の中へ入る。そして、ベッドに横たわる後期を一瞥すると、すぐに視線を外し、部屋全体を見渡し始めた。
その目は、もはや人間の感情を映してはいなかった。 彼の視線は、テーブルの上の薬瓶、ベッドサイドのノートパソコン、そして紗季が隠そうとしていた注射器の空箱を、一つ、また一つと捉えていく。まるで、盤上の石の位置を確認するように。彼の目には、この絶望的な部屋が、一つの難解な詰碁に見えているらしかった。
やがて彼は、初めて紗季に視線を向けた。
「警察は三つの石を取りに来る。一つは、君と彼が交わしたメール。二つ目は、この薬を処方した病院の記録。三つ目は、この注射器だ。物証は揃っている。動機も明確。君は『コウ』に持ち込むことすらできない。五手で詰みだ」
彼の言葉は、刃物のように冷たく、正確に紗季の状況を抉り出した。紗季は、反論する気力もなかった。
「私は……どうすれば…」
かろうじて絞り出した声に、岸波は静かに首を横に振った。
「君は、何もしなくていい」
彼はそう言うと、紗季が隠そうとしていた注射器の箱を、躊躇なく手に取った。
「これからは、私が打つ。君は石だ。思考も感情もいらない。私が置いた場所で、ただ、じっとしていればいい」
岸波は、まるで他人の家を掃除するかのように、淡々と、しかし完璧な手際で、「証拠」を処理し始めた。その姿を見ながら、紗季は理解した。
自分の人生という対局は、この瞬間、彼女の手を離れたのだ。 目の前の男は、彼女の罪を、常人には到底理解できない、彼自身の「棋譜」に書き換えようとしている。それが、どれほど恐ろしく、そしてどれほど美しい結末に至るのか、今の彼女には知る由もなかった。
第二章 盤上の二人
**1.**
翌朝、盤は動き出した。 紗季のアトリエは、鉛色の朝の光の中で、昨日までとは全く違う顔をしていた。かつては創造の聖域だった場所が、今はただの「現場」と化している。制服警官の無遠慮な足音、鑑識官の低い話し声、そして無数の指紋を採取する白い手袋。そのすべてが、紗季と亡き夫の静かな世界を土足で踏み荒らしていく。
その中心に立っていたのが、村上刑事だった。使い古された革靴、皺の寄ったスラックス。鋭いが、その奥に長年の激務による疲労の色が滲む目で、彼は紗季を見ていた。 「水原紗季さんですね。ご主人の件、お悔やみ申し上げます。いくつか、お話を伺っても?」
村上の声は、気遣うような響きの中に、刃物の切っ先のような鋭さを隠していた。紗季は、岸波に言われた言葉を反芻する。『君は石だ。思考も感情もいらない』。彼女は小さく、しかしはっきりと頷いた。
村上は、アトリエを見渡しながら、核心に触れずに外堀を埋めていく。夫の病状、最近の様子、介護の負担。紗季は、岸波とリハーサルした通り、曖昧に、そして悲しみに暮れる未亡人を演じながら答える。だが、村上の目はごまかせなかった。彼の目には、紗季の悲しみが、まるで誰かに書かれた脚本を読んでいるかのように、不自然に映っていた。
**2. **
警視庁の、無機質な取調室。 紗季は、パイプ椅子に浅く腰掛け、正面に座る村上と向き合っていた。テーブルの上には、紗季の悲しみをかき乱すかのように、証拠品の写真が並べられている。夫が交わしていたメールの文面。「生きていても仕方がない」。病院のカルテ。そして、空になった薬瓶。
「ご主人は、周囲に『死にたい』と漏らしていた。ご存じでしたね?」 「……覚えていません」 「紗季さん、あなたはご主人を深く愛していた。彼の苦しむ姿を見るのは、何よりも辛かったはずだ。そのお気持ちは、痛いほどわかります」 村上は、同情という名の揺さぶりをかける。だが、紗季の顔は能面のように変わらない。彼女はただ、黒い碁石のように、そこに存在するだけだった。
村上はため息をつき、今度は語気を強めた。 「彼の最後の夜、あなたがそばにいた。そして、致死量を遥かに超える睡眠薬が投与された。これはどう説明しますか?」 「……分かりません」
村上は、苛立ちを隠さずに机を指で叩いた。まるで、壁に向かって碁を打っているような、虚しい手応えしか返ってこない。この女の沈黙は、雄弁な自白よりも、よほど厄介だった。その沈黙は、彼女自身の意志ではなく、もっと大きな、見えざる誰かの意志によって守られている。村上は、直感的にそう感じていた。
**3. **
その「見えざる何か」は、村上が予想だにしない形で盤上に投じられた。 警視庁捜査一課のフロアが、にわかに色めき立ったのは、その日の午後だった。一人の若手刑事が、血相を変えて係長のデスクに駆け寄る。 「係長! 大変です! 5年前の、世田谷の資産家老婆殺し…あの『笠原事件』です! 真犯人を名乗るメールが!」
「また悪戯か」と誰もが思った。迷宮入りした有名事件には、虚言の自白が付き物だ。だが、添付ファイルを開いた瞬間、フロアの空気が凍りついた。そこには、犯人しか知り得ないはずの、現場に残された遺留品の詳細な特徴や、被害者の最後の言葉までが、異常なほどの正確さで記されていたのだ。
文面は、感情を一切排し、まるで学術論文のように、自らの犯行のロジックを淡々と解説していた。それは、殺人者の告白というより、ある難解な問題を解き明かした、天才数学者の論文のようだった。 村上は、その異様なメールの文面をモニター越しに見ながら、背筋に冷たいものが走るのを感じた。紗季の事件を調べている最中に、なぜ、こんなものが。偶然か? それとも――。
**4. **
白羽の矢が立ったのは、速水恭介だった。 彼は、かつて岸波と並び称された天才棋士であり、若くしてプロ棋界を引退した後は、大学でゲーム理論と認知科学の教鞭をとっていた。その明晰な頭脳と論理的思考力に、警察上層部の一部が目をつけたのだ。
速水は、都心を見下ろす高層ビルの、自身の研究室でその報せを受けた。訪ねてきたのは、旧知の仲である警察幹部だった。 「力を貸してほしい、速水先生。我々は今、人間ではない、『論理の怪物』のような相手と対峙している」
警察幹部が差し出したタブレットに表示された犯行声明を、速水は無言でスクロールしていく。彼の世界は、岸波のそれとは対極にあった。磨き上げられたガラス張りのオフィス、モダンな家具、そして彼自身が纏う、洗練されたスーツと知性。彼は、盤上から降りた後も、「世界」の中に留まり続けた男だった。
「…専門外ですよ。私は、本物の犯罪者ではなく、盤上の思考を読むプロに過ぎない」 速水は一度は固辞しようとした。だが、彼の目は、タブレットの画面に釘付けになっていた。彼の脳が、その文章の背後にある、恐ろしく、そしてどこか懐かしい「思考のリズム」を検出し始めていたからだ。
**5. **
研究室に一人残った速水は、改めて犯行声明を読み返していた。 警察が注目するのは、書かれている「事実」だ。だが、速水が読んでいたのは、事実の裏にある「文脈」であり、「手筋」だった。
なぜ、この単語を選ぶのか。なぜ、この順序で説明するのか。一見、無関係に見える事実の羅列が、ある一点に向かって収束していく構成。相手の思考を誘導し、誤った結論に導くための、巧妙な伏線。 それは、まさしく「棋譜」だった。
彼は、声明文末尾の、被害者の名前に目を留めた。「笠原 静江」。そして、彼の記憶の中から、もう一つの名前が浮かび上がる。
速水は、タブレットを静かにテーブルに置くと、窓の外に広がる東京の夜景を見つめた。ガラスに映る自分の顔が、信じられない、という表情を浮かべている。
「こんな棋譜を書く男を、私は一人しか知らない……」
彼の唇から、囁くような声が漏れた。
「……岸波」
その瞬間、速水にはすべてが繋がった。これは、単なる猟奇事件ではない。かつてのライバルが、現実世界を一つの巨大な碁盤に見立て、仕掛けてきた、壮大で、狂気に満ちた対局なのだ。
速水の脳裏に、警視庁のホワイトボードに貼られた、水原紗季の顔写真が浮かんだ。彼女は、岸波と速水の共通の恩師、故・水原名人の、たった一人の娘だった。
――岸波が、盤上にいる。
速水は、静かに目を閉じた。長い、長い戦いが、今、幕を開けた。
第三章 二つの盤面
**1.**
速水恭介は、動いた。 翌朝、彼は自ら警視庁の門をくぐった。昨日までの、部外者然とした穏やかな物腰は消え、その全身からは、対局開始を告げられた棋士だけが放つ、研ぎ澄まされた闘気が立ち上っていた。
捜査一課の会議室には、村上刑事と数人の捜査幹部が待っていた。速水は挨拶もそこそこに、本題を切り出した。 「昨日いただいた犯行声明…あれは虚構です。ある目的のために、一人の人間によって『創作』された芸術作品と言ってもいい」
会議室がざわめく。村上が眉をひそめて問う。 「虚構…?目的とは何だ。一体誰がそんな手の込んだことを」
速水は、部屋にいる全員の顔をゆっくりと見渡し、静かにその名前を告げた。 「岸波悟。かつての、私のライバルです」
その名前に、若い刑事たちはきょとんとしている。だが、村上や、年配の幹部の間には、微かな動揺が走った。十数年前に彗星の如く現れ、そして消えた天才棋士の名を、彼らは記憶の片隅に留めていた。
「馬鹿な」村上が吐き捨てる。「動機は何だ。彼が、何の関係もない未解決事件の犯人に成りすまして、一体何の得になる?」
その問いに、速水は遠い目をして答えた。 「得などありません。彼の行動原理は、損得ではない。彼独自の、美学と論理です。そして、その根源には…我々の恩師である、故・水原名人がいる」
**2. **
速水の話を聞きながら、村上の脳裏に、取り調べで能面のように無表情だった水原紗季の顔が浮かんだ。岸波悟と、水原紗季。二つの点が、おぼろげな線で結びつき始める。
「理由を話してもらおうか」村上は、腕を組んで速水を促した。
速水は、ゆっくりと語り始めた。それは、彼の個人的な回想であり、岸波という人間を理解するための、唯一の手がかりだった。
――蝉時雨が降り注ぐ、夏の日の午後。蒸し暑い囲碁会所の二階で、少年時代の速水と岸波は、師である水原名人と盤を囲んでいた。攻撃的な棋風の岸波は、盤面全体を支配しようと、名人の石に猛然と襲いかかっていた。
「悟」名人の穏やかだが、芯のある声が響く。「焦るな。盤は広い。すべてを手に入れることはできん」 名人は、盤の隅にある、ささやかだが、黒石に囲まれて完全に生きている白石の一団を指差した。 「棋士が人生をかけて守るべきは、この、自分だけの小さな『地』だ。戦いに敗れることがあっても、この『地』さえあれば、石は死なない。何度でも、そこから再生できる。決して、荒らさせてはならんのだ」
速水は、その教えを「戦略」として理解した。だが、隣にいた岸波は違った。彼は、師の言葉を一言一句、まるで聖典のように、その魂に刻みつけているように見えた。その目は、狂信的とさえ言えるほどの純粋な光を宿していた――。
回想から戻った速水は、村上を真っ直ぐに見つめた。 「岸波にとって、水原紗季は…師が遺した、たった一つの、そして最後の『地』なんです。彼はそれを守るためなら、盤上のすべてを焦土に変えることも厭わないでしょう」
**3. **
その言葉の信憑性を、新たな一手が一瞬にして証明した。 会議室のドアが勢いよく開き、若手刑事が駆け込んできたのだ。 「大変です! 第二の犯行声明が! 3年前に川崎で起きた、強盗殺人事件の!」
すぐにデータがモニターに映し出される。文面は、前回と寸分違わぬ、冷徹で論理的なスタイルで書かれていた。そして、速水はそこに、岸波の恐るべき一着を見出した。
声明の最後に、こう記されていたのだ。 『前回の所業における現場の乱雑さは、若さゆえの過ちであった。今回の所業に至り、私はようやく、抑制の美学を体得した』
捜査員たちは、犯人の自己陶酔的な記述に眉をひそめる。だが、速水は戦慄していた。岸波は、二つの無関係な事件に、架空の「犯人像の成長」という物語を与えることで、それらを一つの連続した犯行であるかのように、完璧に繋げてみせたのだ。
速水は、渇いた唇を舐めた。 「…見事な連携だ。これで二つの石が繋がり、中央に巨大な勢力圏を作り始めた。彼の狙いは、紗季さんの事件を、この『ファントム』の勢力圏という混沌に飲み込ませ、誰の目にも留まらない、価値のない一点にしてしまうことだ」
**4. **
その頃、紗季は、自室の小さなテレビ画面を、音を消して見つめていた。 「連続殺人犯ファントム」のニュースが、日本中を席巻していた。専門家と称する人々が、犯人の異常な心理状態を分析している。彼女の夫の死も、紗季自身の存在も、この巨大な虚構の物語の前では、急速に色褪せていた。
安堵は、なかった。あったのは、自分という一点を守るために、世界という盤面そのものを塗り替えようとしている、あの男の狂気に対する、底知れぬ恐怖だけだった。 部屋の隅には、岸波が最後に残していった一輪のスノードロップが、小さなガラス瓶に挿してある。 花言葉は「希望」。 それは、今の紗季にとって、あまりにも重い言葉だった。
**5. **
警視庁の会議室。重苦しい沈黙が支配していた。岸波の描いた壮大なシナリオの前に、捜査は手詰まりに陥っていた。
沈黙を破ったのは、速水だった。 「我々がファントムを追えば、それは岸波の思う壺です。彼の土俵で戦ってはならない」 「では、どうする?」と村上が問う。
速水は、ホワイトボードに大きく「岸波 悟」と書いた。 「彼のゲームに乗る必要はない。中央の大きな戦いは無視する。我々が攻めるべきは、隅だ」 速水は、その名前を指で強く叩いた。 「岸波悟、本人です。彼の現在の生活、交友関係、収入源…すべてを洗い直す。彼は完璧な論理で虚像を作り上げた。だが、人間である限り、現実世界に必ず歪みが生じているはずだ。その、盤上に現れたほんの僅かな『アジ』を探し出すんです」
「アジ…?」 「囲碁用語です」と速水は短く答えた。「消しきれなかった、弱点の火種のことですよ」
その言葉に、村上の疲れた目に、わずかに光が戻った。相手が仕掛けてきた盤面で戦うのではなく、相手の足元を、現実から崩しにかかる。ようやく、反撃の糸口が見えた気がした。
速水は窓の外を見つめていた。これから始まるのは、警察の捜査という名を借りた、彼と岸波との、静かで、熾烈な「読み」の応酬だ。
第四章 アジと花束
**1.**
速水の提案に基づき、岸波悟に対する徹底的な身辺調査が開始された。だが、現実という盤面は、想像以上に手強かった。 村上率いる捜査チームが調べ上げた岸波の「現在」は、ほとんど空白だった。住民票のある古いアパートは、最低限の家具しかない、まるで禅僧の庵のような部屋。クレジットカードの契約はなく、銀行口座の金の流れは、数ヶ月に一度、数万円が振り込まれるだけ。おそらく、ネット碁の個人指導で得た謝礼だろう。彼は、現代社会のあらゆるネットワークから自らを切り離し、デジタルゴーストとして存在していた。
「どうなってるんだ、この男は」 若手刑事が音を上げる。「霞でも食って生きてるのか。これじゃ、金の流れも、交友関係も、何も追えない」 村上も、苛立ちを隠せない。岸波悟という人間は、物理的には存在するのに、社会的にはほとんど存在していない。そんな男が、どうやって複数の未解決事件の詳細な情報を得て、あれほどの劇場型犯罪を演出できるというのか。岸波の周囲には、謎の霧が立ち込めるばかりだった。
**2.**
突破口は、意外なところから見つかった。 足で稼ぐタイプの、粘り強い若手刑事が、管轄の税務署に保管されていた古い法人登記の記録をめくっていて、それを見つけたのだ。 『屋号:石の花(いしのはな) 事業主:岸波 悟』 事業内容は、生花販売及びフラワーアレンジメント。登記されていた住所は、都心から少し離れた、古い商店街の片隅だった。
村上は、半信半疑でその住所を訪れた。そこには、忘れられたようにひっそりと佇む、本当に小さな生花店があった。看板の文字は掠れ、店構えは、お世辞にも繁盛しているとは言えない。 店番をしていたのは、腰の曲がった老婆だった。 「岸波さん? ああ、あの子なら、今日はもう帰ったよ」 老婆は、岸波のことを「あの子」と呼んだ。彼女の話す岸波像は、村上が思い描いていた「冷徹な怪物」とは、あまりにかけ離れていた。 「口数の少ない子だけどね、花を触っている時だけは、本当に嬉しそうなんだ。人間よりも、花の気持ちの方がよくわかるんだろうねぇ」
村上は、店内に飾られたいくつかのフラワーアレンジメントに目をやった。それは、一般的な花屋のそれとは全く違っていた。使われている花の種類はごく少なく、空間を大胆に使った、まるで前衛芸術のような、静かで、張り詰めた美しさがあった。
**3. **
報告を受けた速水は、自らその「石の花」を訪れた。 彼が店に足を踏み入れた瞬間、その理由がわかった。店内に漂う空気、花の配置、そのすべてに、岸波の「棋譜」と同じ匂いがした。最小限の要素で、最大の効果を生み出す。静寂の中に、計算され尽くした緊張感を漲らせる。それは、岸波の囲碁そのものだった。
速水は、店番の老婆に客を装って話しかけた。 「素晴らしいアレンジメントですね。まるで、一つ一つに物語があるようだ」 老婆は嬉しそうに頷いた。「あの子、花言葉を大事にしていてね。お客さんの話を聞いて、その人に合った花束を、言葉を贈るように作るんだよ」
その時、速水の脳裏に、ある情報が閃光のように過った。紗季の聴取報告書にあった、僅かな記述。「逮捕前に、郵便受けに一輪の花が…」。 「最近、何か特別な注文はありましたか?」 「ああ、そういえば」と老婆は思い出す。「たった一輪だけ、スノードロップを、ってね。大事な人に贈るんだって、あの子が言うのは珍しいことだったよ」
スノードロップ。花言葉は「希望」。 速水は、ようやく岸波の盤面の「アジ」を見つけ出した。完璧な論理で構築されたかに見えた彼の計画に、紗季への個人的な感情という、人間的な「弱点の火種」が、確かに存在していたのだ。 速水は、静かに店を出た。 (花言葉…か。あの男が、そんな感傷的なものに頼るとは。…いや、違う。彼にとって花言葉は感傷ではない。…思考を伝えるための、もう一つの言語なんだ)
**4. **
速水の確信を裏付けるかのように、第三の「捨て石」が投じられた。 今度の犯行声明は、二年前に長野県の山中で起きた、男女の転落死事件。警察は事故として処理していたが、声明は、それが偽装殺人であったことを、完璧な論理で「証明」していた。
捜査本部は、広域捜査への移行で大混乱に陥る。だが、速水が注目したのは、その犯行声明の末尾に添えられた、奇妙な一節だった。
『寂しい峠にひっそりと咲くトリカブトの青は、彼女の瞳の色に似て、あまりにも美しかった』
トリカブト。その花言葉の一つは、「あなたは私を死なせる」。
**5. **
速水は、自室のデスクで、三つの犯行声明を並べていた。 世田谷の資産家老婆殺し。川崎の強盗殺人。そして、長野の偽装事故。 一見、何の脈絡もない事件。だが、それらは岸波という「作者」によって、巧妙に繋げられている。そして、その繋がりを解く鍵は、「花」だった。
一つ目の事件には、暗示がない。開戦の狼煙だ。 二つ目の事件では、犯人の「成長」という物語が語られた。 そして三つ目の事件では、初めて「花」という具体的なモチーフが登場した。まるで、速水に「解いてみろ」と挑戦するかのように。
岸波は、警察という「公の観客」に向けて、派手な犯罪の物語を語っている。だが、その裏で、速水という「たった一人の観客」に向けて、花言葉という暗号を使った、全く別の物語を語りかけているのだ。
速水は、壁に貼られた水原紗季の、憂いを帯びた顔写真を見つめた。 その、あまりにも残酷で、あまりにも美しい計画の全貌が、ようやく彼の中で像を結び始めていた。
「岸波…君は、たった一人のために、世界で最も残酷な花束を作っているのか」
その呟きは、誰に聞かれることもなく、静かなオフィスに吸い込まれていった。
第五章 攪乱の一手
**1.**
速水の研究室は、深夜、静寂に包まれていた。だが、その主の頭脳は、かつてのタイトル戦の前夜のように、激しく回転していた。壁のホワイトボードには、もはや事件の相関図ではなく、奇妙な対照表が作られていた。左列には、ファントムが自供した事件名。そして右列には、速水が植物図鑑や古今の詩集を渉猟して導き出した、花の名前とその花言葉が記されていた。
- 【笠原事件(資産家殺害)】→該当なし。(これはゲームの開始を告げる、第一手。布石だ)
- 【川崎事件(強盗殺人)】→ヒガンバナ(悲しい思い出/再会を願わない)。(現場近くの河川敷に群生。犯人像の「孤立」を暗示)
- 【長野事件(偽装事故)】→トリカブト(あなたは私を死なせる/厭世)。(声明文に直接登場。犯人の「破滅的哲学」を表明)
岸波が紡いでいるのは、単なる犯行声明ではない。これは、一人の孤独な厭世家が、社会への憎悪を募らせ、破滅へと至る、一つの連続した叙事詩だ。速水は、その冷徹な論理と、その裏に隠された狂気に戦慄した。岸波は、自らを怪物に仕立て上げるために、これほどまでに緻密な脚本を用意していたのだ。
**2.**
翌日、速水は村上と二人きりで向き合っていた。 「花言葉、ですか」村上は、心の底から呆れた、という顔で言った。「速水先生、我々が追っているのはシリアルキラーですよ。ポエムの読解会じゃない」
「だからこそ、です」速水は冷静に返した。「これは我々警察や、社会に向けられたメッセージではない。未来の、たった一人の読者に向けられた『遺書』のようなものだ」 「たった一人の読者?」
「水原紗季さんです」速水の声には、確信がこもっていた。「岸波は、自分の計画が成功し、紗季さんが救われた後のことまで読んでいる。いつか、彼女が罪の意識に耐えきれなくなった時…この暗号を解き明かすことで、『岸波は私のために、自ら悲劇の怪物になる道を選んだのだ』と理解できるようにしている。それは、彼女の心を未来永劫縛り付ける、究極の免罪符であり、最も残酷な呪いです」
村上は、返す言葉を失った。速水の推理は、あまりにも飛躍し、あまりにも人間離れしている。だが、岸波悟という男なら、やりかねない。そう思わせるだけの説得力が、その推理にはあった。
**3. **
「もう一度、水原紗季に会う必要があります」 速水は、村上にそう告げた。公式な理由は、過去の恩師との人間関係の再確認。だが、本当の目的は違った。岸波が紗季に残した「希望」という花言葉を持つ、スノードロップ。あの花が、速水の頭から離れなかったのだ。
紗季の住むアパートのドアは、以前よりも固く閉ざされているように感じられた。ドアを開けた紗季は、速水の姿を認めると、怯えたように僅かに身を引いた。彼女は、外の世界のすべてを拒絶しているようだった。
部屋の隅には、あの時と同じガラス瓶に、一本のスノードロップが、最後の力を振り絞るように咲いていた。
**4. **
速水は、当たり障りのない世間話から始めた。そして、不意に、核心に触れる質問を投げかけた。 「先生は、よく盤上の形を『花のようだ』と評しておられました。お元気だった頃の岸波も、よく花の話をしていたのですか?」
その瞬間、紗季の肩が微かに震えたのを、速水は見逃さなかった。彼女の瞳に、一瞬だけ遠い過去を懐かしむような、そしてすぐにそれを打ち消すような、複雑な光がよぎった。
「さあ…昔のことなので、覚えていません」 彼女はそう答えた。だが、その僅かな動揺が、速水には十分な答えだった。岸波と紗季の間には、速水の知らない、花にまつわる記憶が確かに存在する。岸波の「捨て石」は、彼の独りよがりな計画ではなく、紗季の心に直接届くように、緻密に計算された一手だったのだ。
速水は、それ以上は何も聞かず、静かに紗季の部屋を辞した。彼の心は、決まっていた。 岸波の描いた完璧な棋譜を、盤面の外から、乱す。
**5.**
2025年8月8日、金曜日。 その夜、速水恭介は、ある報道番組の単独インタビューに応じていた。彼は、警察の公式な捜査協力者としてではなく、あくまで「ゲーム理論と論理的思考の専門家」として、そして「岸波悟の元ライバル」として、カメラの前に座っていた。
警察が発表していた「衝動的で自己顕示欲の強い、混沌とした殺人鬼」というファントム像を、彼は穏やかに、しかし完全に否定した。
「この『ファントム』と呼ばれている人物は、破壊者ではありません。むしろ、その行動原理は、ある種の歪んだ秩序と美学に貫かれています。彼の犯行声明は、血塗られた供述書としてだけではなく、一人の人間が、自らを怪物へと変えていく過程を記録した、悲劇的な『詩篇』として読み解くべきなのかもしれません。我々は、彼の暴力性ではなく、その行動を支配する、あまりにも冷徹な『知性』にこそ、目を向けるべきです」
この発言は、夜のニュース速報として、瞬く間に日本中を駆け巡った。それは、警察の公式見解を覆し、世間のファントムに対するイメージを根底から揺さぶるものだった。 岸波は、自らを「理解不能な怪物」として社会から断絶させようとした。だが、速水は、その怪物の仮面の下にある「知性」と「美学」を、白日の下に晒したのだ。
それは、盤上ではなく、観客の心理に直接働きかける、禁じ手とも言える一手。 岸波の描いた完璧なシナリオを攪乱する、速水の、明確な反撃だった。
その頃、都内の古いアパートの一室で、岸波悟は、小さなテレビ画面に映る速水の顔を、無表情のまま、じっと見つめていた。彼の周りの空気だけが、絶対零度まで凍りついたかのように、静まり返っていた。
第六章 盤上の応酬
**1.**
速水のインタビューが投下した爆弾は、正確に捜査本部の中枢で炸裂した。 翌朝、警視庁の会議室には、昨日までの期待感が嘘のような、冷え切った緊張が満ちていた。モニターには、各局のワイドショーが速水の顔写真を背景に「専門家、警察方針を批判か」「ファントム=悲劇の創造者?」といった扇情的なテロップを映し出している。
「速水先生、一体どういうおつもりです」 村上は、抑えきれない怒りを声に滲ませた。「我々の公式見解を、テレビの電波に乗せて真っ向から否定した。これで世論は混乱し、犯人を利するだけだ。あなたの目的は何だ!」
速水は、村上の激昂を、静かな目で受け止めていた。 「犯人…岸波を、利するためではありません。彼を、盤上から引きずり出すためです」 彼の声は、変わらず落ち着いていた。 「今の彼は、神の視点でゲームをコントロールしているつもりでいる。安全な場所から、盤上の石を動かしている。その盤そのものを、私が揺さぶったんです。プライドを傷つけられ、自らの脚本を書き換えられた彼は、必ず、感情的な応手を打ってくるはずです」
「応手…?それは、新たな犯行声明か」 「ええ。しかし、次はもっと直接的で、もっと分かりやすい手で来るでしょう。私の『詩人』という見立てを、自らの手で破壊するために」 速水の言葉は、不気味な予言のように会議室に響いた。
**2.**
その頃、岸波悟は、自らが営む生花店「石の花」の奥にある、薄暗い作業場で一人、小さなラジオから流れるニュースを聞いていた。速水の声、そして、それを引用するアナウンサーの声。悲劇の創造者。歪んだ美学。
岸波の表情は、変わらない。だが、彼の指は、一輪の白百合の花びらを、ゆっくりと、しかし確実に、一枚、また一枚と引き千切っていた。純白の花弁が、音もなく作業台に散っていく。やがて、無惨な姿になったそれをゴミ箱に捨てると、彼は店の隅から、棘の鋭いアザミの鉢植えを手に取った。
彼の次の「花束」は、美しくあってはならない。見る者の心をかき乱し、不快にさせ、恐怖させるものでなければならない。速水が自分に着せようとした「悲劇の芸術家」という虚像を、完膚なきまでに破壊するために。
彼は、速水の攪乱を、完璧な読みで理解していた。そして、その挑戦に応えるための、次の一手を静かに準備し始めた。
**3. **
第四の犯行声明は、これまでのEメールとは違い、速水がインタビューを受けたテレビ局の報道部宛に、一通の「手紙」として届けられた。消印は都内。速達。そして、宛名は『速水恭介様』となっていた。
それは、もはや「声明」ではなかった。速水個人に宛てた、剥き出しの「挑戦状」だった。 内容は、一昨年に起きた、未解決の傷害事件に関するものだった。被害者は、ホストクラブで働く若い男性。命に別状はなかったものの、顔に深い傷を負い、その後の人生を大きく狂わされた事件だ。これまでの殺人事件とは、明らかに毛色が違う。
手紙の文体は、これまでの理知的なものとは似ても似つかない、意図的に粗野で、下品な言葉で綴られていた。 『インテリ先生よ。俺の所業に「美学」だの「詩」だの、気取った言葉を並べていたな。反吐が出る。俺にあるのは、ただの破壊衝動だ。あの男の、女に媚びる綺麗な顔が気に食わなかった。だから、壊した。ただ、それだけだ。そこに、お前の好きな「物語」など存在するか?』
手紙は、そう結ばれていた。
**4. **
この第四の告白は、捜査本部を、そして世論を、岸波の狙い通りに大混乱へと陥れた。 「これまでの連続殺人とは、手口も動機も違いすぎる」 「ファントムは、模倣犯の登場に怒って、自ら名乗り出たのか?」 「速水の分析は、完全な的外れだったじゃないか」
村上も、頭を抱えた。速水の理論は、見事に覆された。いや、犯人自身によって、嘲笑うかのように破壊されたのだ。彼は、速水に対する信頼を、そして自らの判断を、見失いかけていた。
その混乱は、水原紗季の心をも蝕んでいた。ニュースで報じられる、ファントムの新たな「告白」。その暴力性と、剥き出しの悪意。彼女が心のどこかで信じようとしていた、「岸波さんは、悲劇的な事情を抱えているだけなのかもしれない」という淡い希望は、粉々に打ち砕かれた。自分が解き放ってしまったのは、やはり、ただの理解不能な怪物だったのだ。彼女は、自室に差し込む光さえも恐れるようになっていた。
**5. **
速水は、研究室で一人、岸波から届いた手紙を、何度も、何度も読み返していた。 表面上の言葉だけを読めば、それは彼の完全な敗北を意味していた。だが、速水は諦めていなかった。岸波ほどの棋士が、これほどまでに感情的で、単純な手を打つだろうか? この盤面の「荒れ」そのものが、岸波の仕掛けた新たな罠なのではないか?
彼は、手紙の文章ではなく、それが語る「状況」に集中した。傷害事件の現場は、新宿・歌舞伎町の雑居ビル。彼は、そのビルの周辺地図をモニターに映し出す。そして、被害者が襲われたとされる路地裏の、その先に何があるかを調べた。
…あった。 地図の隅に、小さな神社の名前を見つけた。境内には、ささやかなバラ園があることで知られている。速水は、指先でそのバラ園をなぞった。
そして、手紙の中の、ある一節に再び目を戻す。 『泣き喚くそいつの顔は、まるで、壊れた人形を抱きしめる子供のようだった』
一見、被害者を嘲る、悪趣味な比喩。だが、その神社の近くには、かつて「人形供養」で有名な寺があった。そして、その寺の跡地に咲くことで有名だったのが、黄色のバラだった。
速水は、花言葉辞典をめくった。 黄色のバラ。花言葉は「嫉妬」「薄らぐ愛」。だが、もう一つの意味があった。
「あなたの許しを乞う」
速水は、静かに目を閉じた。暗号は、まだ生きていた。岸波は、暴力的な言葉の裏に、さらに深い階層のメッセージを隠していたのだ。それは、もはや紗季に宛てたものですらない。この暗号を解読しうる、世界でただ一人の人間――速水恭介に対する、歪んだコミュニケーションだった。
速水は、目を開けた。彼の目に、再び闘志の火が灯る。
「…なるほど。盤面が荒れてきたな、岸波。それでこそ、だ」
相手の応手は、読めている。ゲームは、まだ終わっていない。
第七章 毒を以て毒を制す
**1.**
速水と村上は、深夜の安食堂で、遅い夕食をとっていた。テーブルの上には、食べ終えたラーメンの丼と、村上が持ち込んだ第四の事件の資料が、不釣り合いに同居している。 「…つまり先生は」村上は、割り箸の先で資料を突きながら言った。「この第四の犯行声明は、我々ではなく、先生個人に向けたメッセージだと。そして、その裏には『あなたの許しを乞う』なんていう、花言葉の暗号が隠されていると?」 声には、拭いがたい懐疑の色が浮かんでいた。
「その通りです」速水は、平然と頷いた。「岸波は、私が彼の仕掛けた『詩』を読み解いていることに気づいた。だから、より暴力的で、より下品な言葉でカモフラージュしながら、私にだけわかる形で対話を続けている。挑戦しているんです。『この意味が、お前にはわかるか』と」 「まるで、二人にしかわからない暗号だな」 「ええ。盤外の対話です」
村上は、深くため息をついた。彼の刑事としての経験則が、速水のあまりに文学的な推理を拒絶している。だが、岸波悟という男の異常性を考えれば、その可能性を完全に否定することもできなかった。事実、速水は岸波の思考を、他の誰よりも正確に読み当てているのだから。
**2.**
「ですが、これも岸波の掌の上だ」速水は続けた。「彼が盤面を支配し、我々がその手を読み解くだけでは、永遠に追いつけない。だから、こちらから仕掛ける必要があります」 「仕掛ける? どうやって」
速水は、村上の目を真っ直ぐに見つめた。 「彼の『次の一手』を、予言するんです」 「予言だと?」 「ええ。この花束が、ある男の破滅を描いた悲劇の物語なのだとしたら、次に来るべき章は『裏切り』や『偽り』がテーマになるはずです。男女間の、痴情のもつれ。そして、そのテーマを象徴する花…例えば、ジギタリス。美しい花ですが、毒を持ち、花言葉は『不誠実』。彼は、次の犯行声明で、必ずそういった種類の事件を選んでくる」 速水の声には、狂気と紙一重の、絶対的な確信がこもっていた。 「私が、この『予言』を公にすることで、彼の自由を奪う。彼の脚本に、こちらが一行、書き加えてやるんです」
村上は、言葉を失った。これは、捜査ではない。もはや、二人の天才による、異次元の心理戦だ。失敗すれば、警察と、速水自身の権威は完全に失墜する。だが、この膠着した盤面を動かすには、それしかないのかもしれない。村上は、重い沈黙の末に、小さく頷いた。「…全責任は、あなたが取るんですね」 「もちろんです」
**3. **
その頃、水原紗季は、自室のベッドの上で、膝を抱えていた。部屋は、彼女の心の牢獄と化していた。岸波が残した一輪のスノードロップは、少しずつ萎れ始め、その姿は、まるで希望の終わりを告げているかのようだった。
彼女は、スマートフォンの画面に表示された、速水恭介の顔写真を、何度も見つめていた。大学の公式サイトに載っている、知的な微笑みをたたえた写真。この人は、岸波さんのことを理解している。そして、自分のことも。 『助けて』 その一言を、メールに打ち込んでは、消す。その行為を、彼女はもう何十回となく繰り返していた。岸波との約束を破ることは、彼への裏切りだ。だが、このまま、自分が何者でもない「待つ石」として、巨大な虚構の物語の中に埋もれ、忘れ去られていく恐怖。その二つの恐怖が、彼女の心を押し潰そうとしていた。
彼女の安定は、岸波の計画における、最も重要な前提のはずだった。だが、その最も重要な石が今、自ら盤上を動こうとして、激しく揺らいでいた。
**4. **
速水は、テレビ局ではなく、ある大手出版社の週刊誌に、独占手記を寄稿するという形で、次の一手を打った。それは、より深く、より知的な層に、彼のメッセージを届けるための戦略だった。 記事のタイトルは、『怪物「ファントム」への公開書簡:その花束に隠された、魂の棋譜』。
記事の中で、速水は花言葉の暗号という自らの推理を、丁寧な論理で一般読者にも分かりやすく解説した。そして、その上で、彼は大胆な「予言」を世に問うた。
『…もし私のこの読みが正しいとすれば、「ファントム」の悲劇は、次なる章として「不誠実」というテーマを必要とするだろう。したがって、彼が次に我々に示すのは、男女間の裏切りから生まれた事件の「告白」である可能性が極めて高い。彼は、その象徴として、ジギタリスのような毒を持つ花のイメージを、我々に提示してくるかもしれない。我々が対峙しているのは、単なる犯罪者ではない。自らの魂が崩壊していく様を、リアルタイムで世界に発信し続けている、孤独な表現者なのだ』
この記事は、発売と同時に、爆発的な反響を呼んだ。
**5. **
岸波悟は、その記事を、アパートの部屋の、古びたタブレットで読んでいた。 速水の文章を一字一句、血の通わない指先でスクロールしていく。
読み終えた時、初めて、彼の無表情な仮面に、明確な変化が訪れた。 それは、怒りではなかった。驚きでもない。彼の口元に浮かんだのは、ほんの僅かな、まるで獲物を見つけた獣のような、冷たい笑みだった。
速水は、自分の思考を完璧に読み解いた。そして、あろうことか、自分の「次の一手」を公の場で指し示し、その手を封じようとしてきた。こちらの脚本に、勝手に筆を入れようとしてきた。
それは、神の領域への、許しがたい侵犯だった。
岸波は、ゆっくりと立ち上がった。タブレットの画面には、知的な微笑みをたたえた速水の顔写真が映っている。 岸波の指が、その写真に触れた。そして、次の瞬間。
パリン、と。乾いた音が部屋に響いた。 彼の指の力に耐えきれず、タブレットのスクリーンに、蜘蛛の巣のような亀裂が走っていた。
速水の顔写真が、その亀裂の中心で、歪んで笑っている。
「…面白い」
岸波は、誰に言うでもなく、そう呟いた。 速水が「不誠実」というテーマを提示したのなら、自分は、その遥か上を行く、想像を絶する「次の一手」を打つまでだ。 盤上の主導権は、まだ、こちらにある。
第八章 神の悪手
**1.**
速水の記事が世に出てから、一週間が経った。 盤上は、嵐の前の静けさに包まれていた。警視庁捜査本部は、速水の「予言」に基づき、過去の男女間の痴情のもつれに起因する未解決事件を洗い直し、厳戒態勢を敷いていた。メディアは、固唾をのんで怪物「ファントム」の次の一手を待ち構えている。
その静寂は、速水にとって拷問に近かった。自らが投じた一石は、本当に正しい手だったのか。岸波の思考の海に、的確な波紋を広げることができたのか。それとも、単に盤面を無意味に乱しただけの、素人の悪手に過ぎなかったのか。彼は、自室で何度も自分の記事を読み返し、岸波の思考をトレースし続けていた。
村上からの、苛立ちを隠さない電話が、一日に何度もかかってくる。 「まだ動きはないのか、先生。あんたの予言、当たるんだろうな」 そのたびに、速水は「彼は、必ず応えてきます」と答えるしかなかった。自信と不安の間で、彼の心は揺れ動いていた。
**2.**
その応手は、誰もが予想しなかった、最悪の形で盤上に叩きつけられた。2025年8月17日、日曜日。午後9時。 国内最大の匿名掲示板サイトに、一つのスレッドが立った。タイトルは、『ファントムより、速水恭介と、この国の愚かな大衆へ』。
瞬く間に拡散されたその書き込みは、紛れもなく「ファントム」本人によるものだった。文体は、第四の挑戦状と同じく、粗野で、しかし、燃えるような知性を感じさせるものだった。
『魂の棋譜、悲劇の詩、だと? 自称・天才分析家は、実に面白い物語を創作してくれた。私が過去の亡霊に感傷的な花束を捧げているとでも思ったか。滑稽の極みだ。 いいだろう、教えてやる。お前たちが必死に読み解こうとしている私の「物語」など、初めから存在しない。あれは全て、お前たちのような、意味を求める愚かな人間を嘲笑うための、ただのゲームだったのだ』
書き込みを読んだ捜査員たちは、顔を見合わせた。犯人が、自らの犯行の芸術性を、自ら否定し始めたのだ。
そして、その直後、日本中を震撼させる一文が続く。
『私の行動に、意味も、物語も、美学も存在しないことを証明してやろう。これから、私は最後の「仕事」を行う。それは、過去の清算ではない。未来の、無意味な破壊だ。 ターゲットの名は、水原紗季。 あの凡庸な芸術家の最後の作品であり、偉大なる囲碁棋士が遺した、ただ一つの汚点。私は、彼女という存在を、この盤上から完全に消し去る』
**3. **
警視庁捜査本部は、爆心地と化した。 怒号と、悲鳴に近い指示が飛び交う。村上は、受話器を握りしめたまま、鬼の形相で叫んでいた。 「緊急配備! 水原紗季の身柄をただちに保護しろ! 24時間、一分の隙も見せるな! アパートの周囲、半径500メートル以内にいる不審者は、理由の如何を問わず拘束しろ!」
その矛先は、当然のように速水にも向けられた。 「速水先生ッ!」電話越しの村上の声は、怒りで震えていた。「これが、あなたの言っていた『応手』か! 盤を揺さぶった結果がこれか! あなたは、熊を挑発しただけじゃない、無関係な市民の背中に、的を描いてやったんだぞ!」
速水は、自室の椅子に座ったまま、動けなかった。血の気が引き、指先が氷のように冷たい。村上の言う通りだった。自分の、傲慢な一手は、最悪の事態を招いた。岸波の狂気を、無関係な紗季へと向かわせてしまった。激しい自己嫌悪と罪悪感が、彼の思考を麻痺させた。
その頃、紗季のアパートのドアは、激しくノックされていた。防弾ベストを着用した刑事たちが、彼女をパトカーへと押し込む。何が起きたのか理解できない彼女は、ただ、自分に向けられる無数のフラッシュと、刑事たちの緊迫した表情に、なす術もなく震えていた。 守ってくれるはずだった男が、今や、自分を殺すと宣言している。その、悪夢のような現実を、彼女はまだ受け止められずにいた。
**4. **
速水は、研究室で、モニターに映し出されたファントムの宣言文を、茫然と見つめていた。自分のせいだ。自分が、彼女を危険に晒した。 彼は、生まれて初めて、対局の途中で席を立ちたいという衝動に駆られた。この、岸波との対局から、逃げ出してしまいたい。
だが、彼は棋士だった。どんなに絶望的な盤面でも、相手の一手の意味を、最後まで読み切るのが棋士の務めだ。彼は、震える手でマウスを握り、もう一度、岸波の言葉を、その裏にある意図を、思考の底から拾い上げようとした。
なぜ、岸波は紗季を狙うと宣言した? 彼が本当に彼女を殺したいのなら、宣言などせず、静かに実行するはずだ。こんな声明を出せば、紗季は警察の鉄壁の警護下に置かれ、手出しは不可能になる。つまり、これは「殺害予告」の形をとった、「殺さない」という宣言だ。
では、目的は何か?
その瞬間、速水の脳裏で、バラバラだったすべての石が、一つの星座を描き出した。 岸波の、あまりにも巨大で、あまりにも自己犠牲的な計画の、最後のピースが、恐ろしい音を立てて嵌った。
- 目的1: 私、速水恭介の「悲劇の芸術家」説を、完璧に破壊する。岸波は、ただの「女を狙う卑劣なストーカー」へと堕ちる。
- 目的2: 水原紗季を、日本で最も安全な場所に置く。警察という国家権力に、24時間365日、彼女を「保護」させる。
- 目的3: 警察が自分を逮捕するための、絶対的な大義名分を与える。「未来の犯行予告」は、過去の事件の自白とは比較にならないほど、警察を本気にさせる。
- 目的4: そして、これが最も重要だ。岸波と紗季との間の、あらゆる「関係性の疑い」を、完全に断ち切る。彼が彼女を守るために罪を犯した、などという可能性は、これで完全に消え去る。彼は捕まり、紗季は「怪物に狙われた可哀想な被害者」として、社会の同情の中で生きていける。
これは、岸波が自らの「動機」そのものを、「捨て石」にする、究極の一手だったのだ。愛を、憎悪と宣言することで、その愛を完成させようという、狂気の論理。
速水は、椅子に深く身を沈め、天を仰いだ。 そのあまりに完璧で、あまりに非人間的な「愛」の形に、彼は、もはや戦慄を通り越して、一種の神聖さすら感じていた。
「神の悪手…か」
速水は、誰に言うでもなく呟いた。 神のみが打てる、完璧な一手。そして、人間としては、決して打ってはならない、最悪の一手。
「岸波、君は、神にでもなったつもりか…それとも、ただの…」
言葉は、続かなかった。 岸波が、自らの投了の場所と、その手順を、世界に示した。 終局は、近い。
第九章 投了の場所
**1.**
水原紗季の新しい世界は、無菌室のような静寂と、息の詰まるような閉塞感で満ちていた。 彼女が移されたのは、都内のどこにあるのかも知らされない、警察のセーフハウスだった。窓のカーテンは一日中閉ざされ、ドアの外には常に二人の刑事が立っている。食事は決まった時間に運ばれ、テレビを見ることは許されたが、そこに映し出されるのは、自分を「殺害する」と宣言した男を、日本中の警察が追い回すという、悪夢のような現実だけだった。
肉体は、日本で最も安全な場所に保護されている。だが、彼女の精神は、岸波悟という名の見えざる牢獄に、完全に囚われていた。 なぜ。その問いが、彼女の頭の中を何度も何度も反響する。 なぜ、私を守ってくれたはずのあの人が、私を殺そうとしているの? なぜ、私の犯した一つの罪が、こんなにも多くの人間を巻き込み、世界を狂わせていくの?
彼女は、自分の手を見つめた。愛する夫を、その苦しみから解放した手。すべての始まりとなった、その手。この手の重さが、岸波を怪物に変えてしまった。そう思うと、罪悪感で呼吸が浅くなる。彼女は、岸波の計画通り、「悲劇のヒロイン」として守られながら、その心は、ゆっくりと壊れ始めていた。
**2.**
警視庁の捜査本部は、かつてない規模の包囲網を敷いていた。 岸波悟の顔写真は全国に指名手配され、都内の主要な駅や繁華街では、職務質問が徹底された。何千人もの捜査員が、巨大な碁盤と化した東京の街で、たった一つの黒い石を見つけ出そうと、昼夜を問わず走り回っていた。
村上は、その指揮を執りながら、焦燥感に駆られていた。これだけの物量を投入しているにもかかわらず、岸波の足取りは、ぷっつりと途絶えたままだ。まるで、初めからこの世に存在しなかったかのように。 彼は、速水の「怪物」や「詩」といった非現実的な言葉に、心のどこかで反発しながらも、今回の岸波の動きが、常識的な犯罪者のそれとは全く違うことを、肌で感じていた。これは、逃走ではない。何か、もっと別の、儀式めいた何かなのだ。
「まだ見つからないのか!」 捜査本部に、村上の怒声が響いた。だが、その声は、焦りというよりも、見えざる巨大な相手を前にした、なすすべのなさから来る、悲鳴のようにも聞こえた。
**3. **
速水は、その巨大な包囲網の輪から、一歩外れた場所にいた。 岸波の殺害予告の後、彼の「専門家」としての立場は微妙なものとなり、捜査の第一線からは事実上、外されていた。「あなたの挑発が、事態を悪化させた」――村上のその言葉が、重くのしかかる。
だが、速水は諦めていなかった。警察のやり方は、正攻法すぎる。岸波ほどの棋士が、そんな単純な網にかかるはずがない。彼は、投了の場所を、そしてその手順さえも、とっくに決めているはずだ。 ならば、自分にできることは何か。 岸波に、最後のメッセージを送ることだ。言葉ではない、盤上の作法に則った、静かなる対話を。
速水は、村上に一本だけ電話を入れた。 「村上さん、岸波はもう投了の場所を決めています。警察の皆さんが彼を見つけるのではない。彼が、見つけさせるんです。その前に、私には、彼に伝えなければならないことが一つだけある」
**4. **
速水が向かったのは、再開発で取り壊されるのを待つばかりの、古い雑居ビルだった。その二階に、かつて彼と岸波の恩師、水原名人が営んでいた囲碁会所が、埃をかぶったまま残されていた。 鍵を開けて中に入ると、黴と古い木の匂いがした。午後の光が、汚れた窓ガラスを通して、無数の塵を金色に照らし出している。壁には、名人のかつての対局を報じる、黄ばんだ新聞の切り抜き。そして、部屋の中央には、棋士たちが愛した、使い古された碁盤が、静かに並んでいた。
速水は、師が最も愛用していた、隅に小さな傷のある碁盤の前に座った。そして、持参した古い棋譜集を開き、そこに記された師の名局を、一手順ずつ、再現し始めた。
パチリ、パチリ、と。 静寂な会所に、碁石の音だけが、祈りのように響き渡る。 それは、岸波に対する、速水の無言のメッセージだった。 『聞いているか、岸波。これが、我々の原点だ。師の教えだ。師が愛した、美しい碁だ。君がやっていることは、こんなものではなかったはずだ。君の打つ手は、もっと、静かで、美しかったはずだ』
彼は、ただひたすらに、石を並べ続けた。
**5. **
その報せは、速水が師の棋譜を並べ終えようとしていた、まさにその時だった。 携帯電話が震え、表示されたのは村上の名前だった。
「…捕まえた」 電話の向こうの村上の声は、興奮よりも、むしろ困惑に近い色を帯びていた。 「岸波を、確保した。…だが、信じられん。あいつは、水原紗季のアパートの、真向かいの公園のベンチに、ただ、座っていた。まるで、誰かを待っているみたいに」
その言葉に、速水はすべてを悟った。 岸波は、自らが「紗季を狙っている」という虚構を完璧に演じきり、最も犯人らしく、最もわかりやすい場所で、自らの身柄を警察に差し出したのだ。
速水は、電話を切ると、並べ終えた盤面を見つめた。そこには、師の描いた、完璧な調和と美しさを持つ「地」が広がっている。 その盤面の外で、かつてのライバルは、自らの人生を「捨て石」にすることで、もう一つの、歪で、悲しい「地」を守りきった。
テレビの速報が、岸波悟逮捕のニュースを、興奮気味に伝えている。ヘリコプターの音、記者たちの怒号。 だが、連行される岸波の表情は、速報画面の片隅に映し出されたその顔は、不思議なほど穏やかだったという。 それは、長い、長い対局の末、自らが描いた通りの終局図を完成させた棋士の、静かな満足感をたたえているかのようだった。
公の場での対局は、終わった。 残るは、二人きりの、盤外での最後の問答だけだ。
最終章 終局
**1.**
警視庁の、特別取調室。 壁も、床も、テーブルも、すべてが感情を吸い取るような、のっぺりとした灰色で統一されている。その中央に、岸波悟は座っていた。背筋は、まるでガラスの棒が入っているかのように、まっすぐに伸びている。その姿は、罪を問われる容疑者というより、人生を懸けた対局の、終局を待つ棋士そのものだった。
ドアが開き、速水恭介が一人で入ってきた。村上は、この最後の対話を、速水に一任した。もはや、通常の尋問に意味がないことを、彼も理解していたからだ。 速水は、岸波の正面に腰を下ろした。二人の間には、冷たい金属のテーブルだけがある。だが、彼らの目には、そこに木目の美しい碁盤が、そして、互いの思考という無数の石が見えていた。
**2.**
「見事な、棋譜だった」 速水は、静かに切り出した。それは、刑事の言葉ではなく、好敵手への賛辞だった。 「最初の犯行声明は、意表を突く、盤の隅への布石。二つ目、三つ目で中央に巨大な模様を築き、世間の目をそこに釘付けにした。第四の声明は、私の攪乱に対する、的確な『キカシ』。そして、紗季さんへの殺害予告…あれが、君の人生そのものを投じた、最大にして最後の『捨て石』だった」
速水は、岸波の計画のすべてを、一つ一つ、石を並べるように言語化していく。 「君は、君自身の動機さえも『捨て石』にした。君が彼女を庇ったという、万に一つの可能性さえも消し去るために。彼女を、ただの『可哀想な被害者』という、完璧に安全な『地』に囲い込むために。…そこまで、読んだよ、岸波」
岸波は、何も答えない。ただ、その口元に、ほんの僅かな、影のような笑みが浮かんだように見えた。それは、自らの棋譜を完全に読み解かれたことへの、満足の笑みだったのかもしれない。彼の計画は、完成した。彼は、この対局に、完璧に勝利したのだ。
**3. **
速水は、深く息を吸った。そして、彼自身の、最後の一手を盤上に置いた。それは、盤上の石ではなく、盤外から持ち込まれた、あまりにも人間的な一手だった。
「君の棋譜は、完璧だった、岸波。論理には、一点の隙もなかった。だが、碁盤は、閉じられた世界だ。現実の世界は、君が思うよりも、ずっと気まぐれで、そして、ずっと温かい」
速水は、少しだけ間を置いた。 「一時間前、水原紗季が、すべてを話した。彼女自身の、意志で」
その言葉が、取調室の空気を震わせた。 岸波の、能面のような表情に、初めて、亀裂が走った。
**4. **
彼の世界が、崩れる音がした。 完璧だと思っていた終局図が、たった一つの、計算外の石によって、根底から覆される。 紗季が、自ら盤上に上がり、自らの罪を、自らの言葉で語る。それは、岸波の論理が、そして彼の美学が、決して想定していなかった手だった。 彼の脳裏に、師の顔が、紗季の幼い頃の笑顔が、そして、自らが捨ててきたすべてのものが、走馬灯のように駆け巡る。
守りたかった。ただ、あの笑顔が浮かぶ、ささやかな「地」を、完璧に守りたかっただけだった。そのために、彼は神になろうとした。盤上のすべてを支配する、孤独な神に。
だが、違ったのだ。
取調室の金属のテーブルが、ガタン、と大きな音を立てた。 岸波の拳が、まるで碁石を盤に叩きつけるように、強く、強く、そこに振り下ろされていた。 彼の、完璧に保たれていた姿勢が、初めて崩れた。肩が震え、嗚咽が、喉の奥から獣の呻き声のように漏れ出す。論理の鎧が砕け散り、その下から、剥き出しの、ただの男の魂が慟哭していた。
「……悪手だ…」
涙と嗚咽の合間から、かろうじて絞り出されたその一言。 それは、紗季の行動を責める言葉ではなかった。 彼女に、その、あまりにも人間的で、あまりにも正しい「悪手」を打たせるまで、その心を追い詰めてしまった、自分自身の、神を気取った、愚かな計画に対する、絶望的な敗北宣言だった。
**6.**
裁判は、静かに終わった。 世間を震撼させた怪物「ファントム」こと岸波悟は、すべての罪を認め、その後の生涯を、光の当たらない場所で過ごすことになった。彼は、法廷で一度も、自らの動機を語ることはなかった。 水原紗季は、嘱託殺人という罪で、法の下の裁きを受けた。だが、そこに至るすべての経緯が考慮され、彼女が再び社会に戻る日は、そう遠くないものとなった。
**7. **
二年後の、秋。 木々が赤や黄色に染まる、穏やかな午後の光の中で、紗季は、父と夫が眠る墓の前に立っていた。彼女の表情には、もう、かつてのような怯えや罪悪感の影は薄く、静かな決意のようなものが宿っていた。
彼女は、持ってきた菊の花を供えると、静かに手を合わせた。 立ち上がって帰ろうとした、その時。彼女は、墓石の根元に、何かが置かれているのに気づいた。
それは、手のひらで磨かれたように艶のある、黒い碁石と、雪のように白い碁石だった。 二つの石が、まるで、長い戦いを終えた二人の棋士のように、静かに、寄り添うように、そこに置かれていた。
誰が、いつ、置いたのか。彼女にはわからない。 だが、その二つの石を見つめていると、涙が、彼女の頬を静かに伝った。 それは、単なる悲しみの涙ではなかった。奪い、奪われ、守り、壊し、そして、あまりにも多くのものを失った、あの壮絶な対局のすべてを、鎮魂するような、温かい涙だった。
紗季は、もう一度、深く頭を下げた。 そして、顔を上げると、前を向いて、ゆっくりと歩き出した。 空は、高く、青く澄み渡っていた。 盤上の戦いは、終わり、新しい一日が、始まろうとしていた。
(了)





















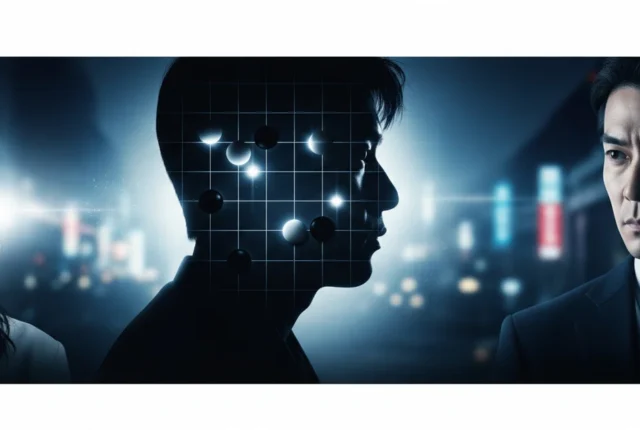














この記事へのコメントはありません。